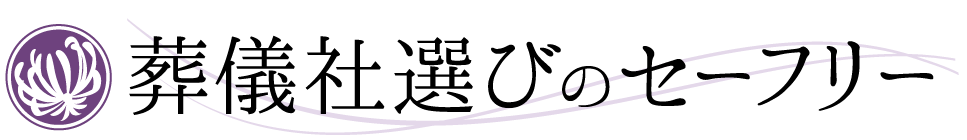家族葬専用会館とは?一般葬儀施設との違い・特徴・費用相場を徹底解説!
突然の大切な方との別れに直面し、どのような形式の葬儀を選ぶべきか悩まれている方も多いのではないでしょうか。
「故人は派手な葬儀を望んでいなかった」「家族だけでゆっくりとお別れの時間を過ごしたい」
そんな想いから家族葬を検討される方が増えています。
しかし、家族葬専用ホールについて、一般の葬儀場より設備が劣るのではないか、親族から理解を得られるだろうか、といった不安の声も聞かれます。実際には、家族葬専用ホールは、少人数での葬儀に特化した設備とサービスを備え、故人との大切な時間を過ごすための工夫が随所に施されています。
この記事では、家族葬専用ホールの特徴や一般的な葬儀ホールとの違い、具体的な費用や選び方のポイントまで、実際の利用者の声を交えながら詳しく解説します。大切な方との最期のお別れの形を決める際の、信頼できる情報源としてご活用ください。
この記事で分かるポイントは?
家族葬専用ホールとは?

家族葬専用ホールは、大規模な一般葬ではなく、家族や親しい方々との温かな最期のお別れを希望される方のために生まれた新しい形の葬儀施設です。
「家族だけで静かにお別れをしたい」「大げさな葬儀は故人の意思に反する」。
そんな想いに応えるために誕生したのが家族葬専用ホールです。家族葬専用ホールでは、従来の葬儀場では当たり前とされていた形式的な慣習から解放され、故人らしい、そして遺族の方々の想いに寄り添ったお別れの時間を過ごすことができます。
具体的には以下のような特徴があります。
- 一般的な葬儀ホールの1/3程度の広さ
- 20名から50名程度の参列者に最適化
- 自宅のリビングルームのような温かみのある内装
廊下や控室も、他の参列者と鉢合わせることのないよう、プライバシーに配慮した設計となっています。
家族葬ホールの種類と規模の違い
家族葬専用ホールは、利用するご家族の状況に応じて選択できるよう以下のようないくつかのタイプが用意されています。
| タイプ | 特徴 |
|---|---|
| 完全個室型 | マンションの一室のような完全プライベート空間で、10名程度までの密葬に最適 他の参列者と顔を合わせることなく、完全なプライバシーが確保されます |
| 一般住宅改装型 | 一軒家を改装した20名程度収容可能な施設 自宅での葬儀のような親密さと、葬儀施設としての機能性を両立 庭付きの施設では、故人が好んだ花を飾ることもできます |
| ホテル形式型 | 30名から50名程度に対応し、宿泊施設や食事スペースを併設 遠方からの参列者への配慮が必要な場合に適しています |
家族葬ホールの主な提供サービスと機能
家族葬専用ホールでは、葬儀に不慣れな方でも安心して利用できるよう、以下のような必要なサービスをワンストップで提供しています。
- 葬儀アドバイザーによる24時間相談対応
- 近隣の医師による死亡診断書の手配
- 役所への届け出代行
- 火葬場との調整
- 返礼品の手配や案内状の作成補助
- 近隣飲食店への料理発注代行
特に、直葬(火葬のみ)から一日葬、伝統的な二日葬まで、ご家族の意向に応じた柔軟な時間設定が可能です。また、高齢の参列者が多い場合は、車での送迎サービスを手配することもできます。
このように、家族葬専用ホールは、大規模な葬儀場にありがちな形式的で冷たい雰囲気を排除し、故人との最期の時間を大切に過ごせる空間として、多くの方に選ばれています。
家族葬ホールの施設内容とサービス内容

近年、家族葬を検討される方が増える中で、実際の施設やサービスの内容を知りたいという声が多く寄せられています。ここでは、家族葬専用ホールが提供している設備やサービスの実態について解説していきます。
家族葬専用ホールと一般的な葬儀ホールの違い一覧表
| 比較項目 | 家族葬専用ホール | 一般的な葬儀ホール |
|---|---|---|
| 規模 |
|
|
| 収容人数 | 20~50名程度 | 100名以上 |
| 施設の特徴 |
|
|
| 祭壇設備 |
|
|
| 駐車場 |
|
|
| 控室・待合室 |
|
|
| ご高齢者対応 |
|
|
| 費用構造 |
|
|
| スタッフ対応 |
|
|
| 食事・供花 |
|
|
式場の特徴
家族葬専用ホールの基本設備は、一般の葬儀ホールと比べてコンパクトながら、必要な機能を効率的に配置することで、参列者の負担を軽減する工夫がなされています。
式場は、一般的な葬儀ホールの3分の1程度の広さで設計されており、以下のような特徴があります。
- 20~50名程度がゆったりと着席可能な広さ
- 可動式の椅子で、参列人数に応じて配置変更が可能
- 祭壇までの距離が近く、故人を身近に感じられる設計
- 写真や思い出の品を飾るための専用スペース
- 宗教を問わない祭壇設計(仏式・神式・無宗教対応)
特に宗教対応については、特定の宗教様式に固定されない柔軟な設計が採用されており、仏式や神式、無宗教など、様々な形式での葬儀進行が可能となっています。
控室・待合室の特徴
控室は10畳から15畳程度のスペースが標準的で、防音設計により外部の音が気にならない環境が整えられています。長時間の滞在に配慮し、以下のような特徴を備えています。
- プライバシーを重視した完全個室(10~15畳程度)
- 仮眠用ベッドや着替えスペース完備
- シャワールーム(施設による)
- 冷蔵庫、電子レンジなどの簡易キッチン設備
- 木目調の落ち着いた内装と、防音設計による静寂な空間
待合室は多くの場合、以下に挙げる特徴を持っています。
- 8~12名程度が利用できる和室または洋室
- お茶やコーヒーのセルフサービスコーナー
- エアコン完備の快適な空調管理
- Wi-Fi環境(一部施設)
駐車場やアクセス面の配慮と利便性
アクセス面については、高齢者や体の不自由な方への配慮が重視されています。施設内は段差を最小限に抑えたバリアフリー設計が基本となっており、動線もシンプルで分かりやすい設計が特徴です。
駐車場は、家族葬の規模に合わせて10台前後のスペースが確保されているのが一般的です。公共交通機関でのアクセスについても、最寄り駅からのアクセス方法が整備されており、タクシー会社と提携している施設も増えています。
宿泊設備の有無と利用の可否
宿泊機能については、施設によって対応が分かれています。宿泊設備を備えた施設では、4室から6室程度の個室が用意されており、シャワーやトイレなどの設備を完備しています。
宿泊設備がない施設の場合は、近隣のホテルと提携し、優待料金での宿泊手配を行うケースが一般的です。遠方からの参列者が多い場合は、宿泊施設の選択肢を事前に確認しておくことが重要です。
料理や供花の提供オプション
家族葬では、会食や供花についても、少人数での実施を前提としたサービスが提供されています。料理については、5名から30名程度の会食に対応したメニューが用意されており、食事制限のある参列者への個別対応も可能です。
供花は、コンパクトな祭壇に合わせた規模で提供されるのが特徴で、季節の花を中心としたナチュラルなデザインが主流となっています。
ホールごとに異なる特色あるサービス
各施設では、基本的なサービスに加えて、独自の追悼サービスも展開されています。以下に挙げるような、家族葬ならではの特徴的なサービスが提供されているホールが多いです。
- 故人の思い出写真のスライドショー上映
- 参列者からのメッセージカード作成
- 記念品として遺影や供花の撮影サービス
- 故人の趣味や好みを反映した空間演出
- 戒名の相談や授与の手続き代行
- 火葬場への案内・手続きサポート
- 役所への各種届出代行
24時間対応の相談窓口を設けている施設も多く、突発的な事態にも対応できる体制が整えられています。
家族葬専用ホールのメリット

家族や親しい方々と心を込めてお別れをしたい。そんな想いに応える家族葬専用ホールには、様々なメリットがあります。実際の利用者の声を交えながら、具体的にご説明していきましょう。
プライベートな空間で心ゆくまで故人を偲べる
家族葬専用ホールの最大の特徴は、他の参列者を気にすることなく、プライベートな空間で故人との時間を過ごせることです。「普段は涙を見せない父が、ゆっくりと母に語りかけることができた」「子どもたちが故人の思い出を自由に話せる雰囲気があった」といった感想を持たれるご遺族が多いです。
個室型の安置室では、深夜でも故人と面会が可能です。仕事や育児で日中の参列が難しい家族も、都合に合わせて故人との時間を持つことができます。
また、一般の葬儀場では難しい、ペットとの最後のお別れにも対応している施設も増えています。
小規模だからこそ実現できるシンプルで温かい葬儀
家族葬専用ホールでは、参列者が少ないからこそ可能な、きめ細やかな配慮が随所に見られます。式場の座席配置は、遺族全員が故人の近くで座れるよう工夫されており、まるで家族の団らんのような温かな雰囲気の中で、お別れの時間を過ごすことができます。
宗教面でも柔軟な対応が可能です。「故人が生前、堅苦しい葬儀は望んでいなかった」という場合には、読経を短くしたり、好きな音楽を流したりと、故人らしさを大切にした葬儀進行を実現できます。
家族の意向に沿った柔軟なプランの実現
一般的な葬儀場では、既存のプランに合わせざるを得ないことも多いですが、家族葬専用ホールでは、家族の意向を最優先に考えた柔軟な対応が可能です。例えば、「朝一番の火葬から、夕方に小さな法要を行いたい」といった具体的な要望にも、きめ細かく対応してくれます。
また、急な参列者の増減にも柔軟に対応。当日になって親戚が駆けつけてくれた場合でも、座席の追加や料理の手配など、臨機応変な調整が可能です。
スタッフが少人数葬儀に特化
家族葬専用ホールのスタッフは、少人数での葬儀進行に豊富な経験を持っています。「大規模な葬儀しか経験がない」というスタッフではなく、家族葬ならではの配慮点を熟知したスタッフが対応するため、細やかなサポートを受けることができます。
特に、突然の死別で葬儀の経験がない遺族に対しては、基本的な作法から必要な手続きまで、一つ一つ丁寧に説明してくれます。「わからないことを気軽に相談できた」「親身になって話を聞いてくれた」という声が多く寄せられています。
費用の透明性と納得感
家族葬専用ホールでは、必要最小限の設備とサービスに特化しているため、費用の内訳が明確です。一般的な葬儀場で発生しがちな、想定外の追加費用も最小限に抑えられます。
例えば、大規模な葬儀場では当たり前とされていた、大量の供花や返礼品などの付帯費用を、家族の意向に応じて適切な規模に調整可能です。「予算内で故人らしい葬儀ができた」「無駄な出費を抑えられた」という声も多く聞かれます。
見積もり時には、基本料金に含まれるサービスと、オプションで追加できるサービスが明確に区分されており、予算に応じた選択が可能です。突然の出費に不安を感じる遺族の方々にとって、この費用の透明性は大きな安心材料となっています。
家族葬専用ホールのデメリット

家族葬専用ホールには多くのメリットがある一方で、検討すべき課題もあります。ここでは実際の利用者の体験から、想定しておくべき点を詳しくお伝えします。
参列者数に制限があることへの注意点
家族葬を検討される際、最も慎重に考えたいのが参列者の範囲です。「親戚一同に連絡しなかったことで、後から問題になってしまった」「故人の職場の同僚から参列したかったと言われ、申し訳なかった」という体験談も少なくありません。
特に、故人が地域社会で活動的だった場合や、広い人脈をお持ちだった場合は、家族葬という形式自体を慎重に検討する必要があります。また、親族間での葬儀形式に対する考え方の違いが、後々の人間関係に影響を及ぼすケースもあります。
このような事態を避けるために、家族葬を選択する際は、故人の社会的な立場や人間関係を十分に考慮し、参列できない方への配慮として、後日の報告や偲ぶ会の開催などを検討することをお勧めします。
規模による設備の制約とその影響
家族葬専用ホールは、その性質上、設備面での制約があります。例えば、突然の参列者増加に対応できない場合や、大規模な供養壇を設置するスペースがないといった物理的な制限があります。
また、駐車場の収容台数も限られているため、「遠方から車で来られる参列者が多い場合、近隣の有料駐車場を案内せざるを得なかった」といった課題も報告されています。さらに、待合室や控室の数も限られているため、複数の親族グループで利用する場合、十分なスペースが確保できないこともあります。
一部の宗教儀式に対応できない場合
家族葬専用ホールでは、大規模な宗教儀式への対応が難しい場合があります。特に、仏式の場合、本来の形式に則った読経や導師の人数が制限される可能性があります。「菩提寺の住職から、正式な葬儀を勧められて困った」という声も聞かれます。
また、神式や特定の宗派による独自の儀式を執り行う場合、施設の構造上、本来の作法通りに実施できないことがあります。事前に菩提寺や神社と相談し、簡略化した形式での執行について合意を得ておくことが重要です。
遠方からの参列者が多い場合の配慮点
家族葬専用ホールでは、宿泊施設が併設されていない場合が多く、遠方からの参列者への対応に課題が生じることがあります。「高齢の親族が遠方から来るため、近隣のホテルを手配する必要があった」「前泊・後泊の手配が煩雑だった」という体験も少なくありません。
また、公共交通機関でのアクセスが不便な立地の場合、参列者の送迎に関する調整が必要となります。特に、高齢の参列者が多い場合は、交通手段の確保が大きな課題となることもあります。
これらのデメリットは、事前の準備と対策により、ある程度軽減することが可能です。
家族葬専用ホールを選ぶべき状況や目的

人生最後のお別れの形として、家族葬を選択される方が増えています。では、どのような状況で家族葬専用ホールを選ぶことが望ましいのでしょうか。
故人の意思を尊重するケース
「大げさな葬式は避けてほしい」「身内だけで静かに送ってほしい」という故人の生前の希望があった場合、家族葬はその想いに応える最適な選択となります。特に近年は、自身の葬儀について家族と話し合っておられる方も増えており、「母は生前から、家族だけで静かにお別れをしたいと話していました」という声をよく耳にします。
遺族の状況による選択
配偶者が高齢の場合、長時間の葬儀は大きな負担となります。「91歳の母が喪主となるため、負担の少ない形式を探していました」「父の体調を考えると、大勢の弔問客を迎えることは難しいと判断しました」といった理由で、家族葬が選ばれています。
現代の社会状況に応じた選択
核家族化が進み、地域とのつながりが希薄になっている現代では、大規模な葬儀を行う必要性を感じない方も増えています。また、長期の療養生活を経て、親しい方々との別れの時間を十分に持てていた場合にも、家族葬が選ばれる傾向にあります。
経済的な理由
一般的な葬儀と比べて費用を抑えられることから、「必要最小限の費用で、心のこもった葬儀を実現したい」という方にも適しています。ただし、これは決して質素な葬儀というわけではなく、むしろ一人一人に向き合える、充実したお別れの時間を持つことができます。
家族葬専用ホールを利用する場合の流れ

突然のお別れに直面し、何から始めればよいのか戸惑われる方も多いと思います。ここでは、家族葬専用ホールを利用する際の具体的な流れと、実際の体験に基づく重要なポイントをご説明します。
選択時の注意点と失敗しないためのコツ
家族葬専用ホールを選ぶ際、最も重要なのは事前の現地確認です。なぜなら、写真やウェブサイトの情報だけでは、実際の雰囲気や使い勝手が分からないためです。
「写真で見た以上に天井が低く圧迫感がありました」「安置室が想像以上に狭く、家族全員で集まることができませんでした」という声も聞かれます。可能な限り、実際の空間を確認することをお勧めします。
アクセスの利便性
確認すべきポイントの一つ目は、アクセスの利便性です。特に、高齢の参列者が多い場合は、駅からの距離や段差の有無、エレベーターの設置状況などを確認します。
「母が車椅子を使用しているため、バリアフリー設備が整っているかどうかを重視しました」という体験談も多く寄せられています。
収容人数
二つ目は、実際の収容人数です。カタログなどに記載された定員は、ゆとりのない最大数である場合が多いため、実際の空間で座席の配置などを確認することが重要です。
「30名収容と聞いていましたが、実際に並べてみると、快適に座れるのは20名程度でした」という例もあります。
スタッフの対応
三つ目は、スタッフの対応です。葬儀は、専門知識が必要な一方で、デリケートな感情にも配慮が必要な場面です。
下見の際のスタッフの説明が丁寧で、不安や疑問に真摯に答えてくれるか、遺族の気持ちに寄り添った対応ができているかを見極めることが大切です。
「見積もりの説明が一方的で、こちらの希望を聞く姿勢が感じられませんでした」という残念な経験を避けるためにも、事前の対応を重視してください。
見積の内容
見積もりの内容確認も重要です。基本料金に含まれるものと、オプション料金が発生するものを明確に区分し、説明を求めましょう。
「当日になって、必要な物品のほとんどが追加料金と分かり、予算をオーバーしてしまいました」という事態は、事前の確認で防ぐことができます。
特に注意したいのは、安置の期間や面会時間の制限です。「仕事帰りに毎日寄りたいと思っていましたが、夜間の面会に制限があることを後から知りました」という声も聞いたことがあります。
24時間対応なのか、特定の時間帯しか面会できないのかなど、具体的な利用条件を確認することが重要です。
事前予約や申し込みの流れ
もしも病院や施設で最期を迎えられることが予想される場合、医師から終末期のお話を伺った段階で、家族葬専用ホールへの問い合わせを始めることをお勧めします。「予期せぬ事態でしたが、事前に情報を集めていたおかげで、冷静に対応できました」という声も多くお聞きします。
申し込みの際には、以下の点について具体的な確認が必要です。まず、ご遺体の安置について。「病院の霊安室を何時まで利用できるのか」「搬送のタイミング」「家族葬専用ホールでの安置開始時期」など、時間の流れを把握しておくことが重要です。
また、親族への連絡のタイミングも重要なポイントです。「家族葬にすることへの理解を得るため、まず近親者に電話で状況を説明しました」という体験談にもあるように、葬儀の形式について、できるだけ早めに家族間で合意を形成することが、後々のトラブル防止につながります。
葬儀前後のスケジュールと準備の流れ

葬儀の日程が決まったら、まず参列予定の方々への連絡を行います。家族葬は参列者が限られるからこそ、一人一人への丁寧な連絡が可能です。特に高齢の方には、交通手段の確認や、必要に応じて送迎の手配も検討しましょう。
施設との打ち合わせでは、以下の点を具体的に決めていきます。
- お花や供物の種類と量
- 故人の遺影や思い出の品の展示方法
- お食事を用意する場合はその内容
「家族だけだからこそ、一つ一つのものに故人への想いを込めることができました」という声も多く聞かれます。
宗教者への連絡も重要です。「特定の宗派にこだわらず、故人の人生に寄り添った言葉をかけていただける方にお願いしました」という選択も増えています。
家族葬だからこそ、形式にとらわれず、故人と家族の希望に沿った選択が可能です。
利用者の役割分担
当日は、限られた家族メンバーで協力し合うことが大切です。以下に挙げる必要最小限の役割を決めておくと安心です。
- リーダー
- 受付
- 案内
- お布施や金封の管理
「若い世代の家族が中心となって動くことで、高齢の両親は故人との時間に集中できました」という体験談も参考になるでしょう。
葬儀社のスタッフは、会場設営から受付の準備、証明写真の撮影、火葬場との連絡調整まで、基本的な実務を担当します。ただし、細かな指示出しは家族側で行う必要があるため、主となる担当者を決めておくことをお勧めします。
当日の服装や持ち物、マナーについて
家族葬だからといって、基本的な慎みの姿勢は大切です。服装は一般的な葬儀と同様、黒を基調とした喪服が基本となります。
ただし、「故人が好きだった小物を身につける」「明るめの装いを心がける」など、故人の意向を反映した選択をされる方も増えています。
持ち物は、数珠と念珠入れ、覚え書きを記入するためのノートなど、必要最小限で構いません。
写真撮影は家族間で事前に相談しておくことが重要です。「最後の思い出として残したい」という意見と、「厳かな雰囲気を保ちたい」という考えの両方があるためです。
事前に知っておくべき段取りと注意点
家族葬は小規模だからこそ、細やかな準備が可能です。特に重要なのが、参列者への事前連絡です。家族葬という形式を選んだ理由を丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。
「突然の決定だったため、伯父や伯母などに説明が行き届かず、後になって不満の声が上がりました」という経験談も多く、事前の配慮が必要です。
また、当日までの時間の使い方も重要です。「家族だけの時間だからこそ、一人一人が故人との思い出を語り合える場面を作りたい」「子どもたちにも、おじいちゃんとのお別れの時間をしっかり持たせてあげたい」といった想いを実現するためには、綿密な時間配分が必要です。
家族葬専用ホールの費用相場

家族葬専用ホールの基本プランは、通常30万円から80万円程度が相場です。基本プランに含まれる内容は施設によって異なりますが、一般的に以下の項目が含まれます。
- 施設使用料(式場、控室、待合室)
- 祭壇と装飾品の基本セット
- 司会進行料
- ご遺体の安置料
- 霊柩車代(基本距離内)
- 受付用具一式
「一般葬の3分の1程度の費用で、心のこもった葬儀ができました」という声も多く聞かれます。
オプションサービスの料金と相場
基本プランの他に、必要に応じて選択できるオプションサービスがあります。主なものには以下があります。
- お料理:一人3,000円~8,000円程度
- お花の追加:10,000円~50,000円程度
- 位牌:30,000円~80,000円程度
- 遺影写真の加工編集:15,000円~30,000円程度
- 会葬礼状:一枚100円~300円程度
追加費用が発生するケースと対策
予期せぬ追加費用が発生するケースとして多いのが、安置期間の延長です。「親族との日程調整に時間がかかり、安置料が余分にかかってしまいました」という例もあります。
また、火葬場までの距離が基本料金の範囲を超える場合も、追加料金が発生します。これらを防ぐためには、見積もり時に以下の点を確認することが重要です。
- 基本料金に含まれる安置期間
- 延長料金の発生条件と金額
- 火葬場までの距離制限と追加料金
- キャンセル料の発生条件
家族葬ホールでコストを抑えるポイント
必要な費用を抑えつつ、大切な方との最期のお別れを実現するためのポイントをご紹介します。
まず、日程の選択です。平日と休日では料金が異なることが多く、平日を選ぶことで費用を抑えられます。
また、会食を簡素化したり、お花を必要最小限に抑えたりすることで、大幅な節約が可能です。「故人が好きだった花一種類だけを飾り、その分を参列者全員でゆっくり過ごす時間に充てました」という選択も増えています。
ただし、費用面だけを重視しすぎると、後悔につながることもあります。「もう少し丁寧なお別れの時間が持てれば良かった」という声も聞かれます。
大切なのは、故人との最期の時間にふさわしい予算配分を考えることです。
まとめ
大切な方との最期のお別れの形として、家族葬という選択肢が広がっています。家族葬専用ホールは、大規模な葬儀場とは異なり、ご家族の心に寄り添った温かな空間で、故人との大切な時間を過ごすことができます。
施設選びで最も重要なのは、複数の家族葬専用ホールを比較検討し、実際に足を運んで確認することです。写真やウェブサイトだけでは分からない雰囲気や、参列予定人数に対する空間の広さ、アクセスの利便性なども、ご自身の目で確かめることが大切です。
そして、2、3カ所のホールから相見積もりを取ることをお勧めします。
家族葬は、故人の意思を尊重しながら、近しい方々との心のこもったお別れを実現できる形式です。ただし、参列者の範囲については、故人の人間関係や社会的立場を踏まえて慎重に検討する必要があります。
まずは、このサイトで紹介している家族葬専用ホールに問い合わせ、具体的な情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。
よくある質問
家族葬で親戚や故人の友人から後々問題になることはありませんか?
親族間の不和を避けるためには、以下のような対応が効果的です。まず、家族葬を選択した理由(故人の遺志、高齢の遺族への配慮など)を、親族に丁寧に説明することが重要です。また、親族への事前連絡と相談を怠らず、必要に応じて「後日、お別れの会を開催する」といった配慮も検討します。特に、故人の兄弟姉妹には個別に連絡を入れ、理解を得ることをお勧めします。
家族葬専用ホールの見学や相見積もりは、いつ頃から始めるべきですか?
医師から終末期の告知を受けた段階で、情報収集を始めることをお勧めします。特に、安置設備や面会時間、基本料金に含まれるサービスは、施設によって大きく異なります。実際の利用者からは「慌ただしい時期だからこそ、事前に2~3カ所は見学しておくべきだった」という声も。施設の雰囲気やスタッフの対応を直接確認することで、いざという時の判断材料になります。
家族葬の費用はどのように抑えられますか?
費用を適切に抑えるためのポイントがいくつかあります。まず、基本プランに含まれるものと、オプションサービスの内容を明確に確認します。例えば、平日利用での割引制度を活用したり、供花を必要最小限に抑えたり、会食を簡素化したりすることで、30万円台での葬儀執行も可能です。ただし、「後悔のない送り方」を第一に考え、特に故人との最後の時間に関わる設備やサービスについては、十分な検討が必要です。